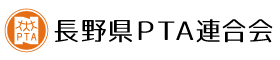第2分科会 家庭教育(健康・食育)
スケジュール
10月18日(土)
- 12:00
開場 - 12:30
受付開始 - 13:00
開会式 - 13:10
<研究発表①>
栃木市PTA連合会 - 13:35
<講演>
講師:田中 雅子 氏 - 14:40
休憩 - 15:00
<研究発表②>
須坂市立須坂東中学校 - 15:20
パネルディスカッション
テーマ
「結」明るい未来のために、親も子も元気に過ごすための食育
趣旨(現状の課題)
子どもたちを取り巻く教育環境は大きく変わってきています。これからの社会を元気に過ごすための「生きる力」を育む家庭教育の重要性を再認識したいものです。
生きていくうえで最も重要であり毎日欠かすことのできない「食」、欠食や学校での給食について考え、忙しい毎日の中でもできる「食育」について共に学びを深めていきましょう。
学びのポイント
- 必要とされる「生きる力」
- 「食育」の重要性
- 家庭・学校・地域での「食育」
講師

田中 雅子 氏
NPO法人長野県食育協会 理事
- 「NPO法人日本食育協会」食育指導士
- 「NPO法人長野県食育協会」理事・評議員
- 「健康日本21」ヘルスサポーター
- 東洋古典医学「黄帝内経素問・霊柩研究会」主宰 ユネスコ記録遺産
- 「医心方研究会」主宰 国宝日本最古医学書
- 古典医学から未来社会へ
子どもたちの未来のために、講演会、学習会、研究会を続けている
研究発表
テーマ
「学校・家庭・地域」と協働・連携したPTA活動の促進
~とちぎ未来アシストネット事業との連携をとおして~
発表校
栃木市PTA連合会(栃木県)
発表者

大類 竜矢(栃木市PTA連合会事務局(栃木市教育委員会事務局生涯学習課))
発表内容
学校・家庭・地域の連携を深め、地域ぐるみで子どもたちの「生きる力」を育むための「とちぎ未来アシスネット事業」の研究を進めており、その成果について発表する予定。
本研究は、「学校・家庭・地域」の協働・連携によるPTA活動の促進を目的とし、とちぎ未来アシストネット事業(地域学校協働活動)との連携を通じて、PTAの活性化と教育環境の向上を図ったものである。
研究では、市内小中学校のPTA会長や校長を対象にアンケートを実施し、その結果を踏まえて、①アシストネット事業の認知度向上、②保護者と地域住民ボランティアとの連携強化、③PTA組織や行事の在り方の見直し、の三点を重点的に取り組み、保護者負担の軽減や学校との連携強化などを目指した。
具体的な取組としては、広報紙の作成や説明会の開催、ボランティア交流会や学校運営協議会での協議、さらにはPTA行事への地域参加を推進し、その効果を検証した。
その結果、地域ボランティアとの協働により、役員の負担軽減とPTA活動の活性化が実現した。保護者は学校や地域とのつながりを深め、授業理解や子育て相談の機会を得ることができた。学校にとっても、地域の応援団の存在を実感することで教員の負担軽減や教育環境の充実につながった。さらに児童生徒にとっては、多様な大人との関わりを通じて自己肯定感が育まれ、地域への愛着を深める効果が確認された。
今後の課題として、「PTA行事等の確実な引継ぎの仕組みづくり」「PTA・学校・地域が対等な立場で協議できる関係づくり」などが明らかとなった。
パワーポイントのデータはこちら> PPT
テーマ
自作弁当の日の取り組みで学校全体の食育を推進
発表校
須坂市立東中学校PTA(長野県)
発表者

松峯 昌男(上高井郡市PTA連合会 会長)
発表内容
食育に関する生徒・教職員の意識の変化と活動の広がり
・自作弁当の日
・学校での教科横断的な学習
須坂市立東中学校は、長野県の北部、標高536mでスカイツリーの展望回廊よりやや高いところに位置し、学ぶ心と思いやる心、そして鍛える心を磨き自立していく生徒の育成を願った三心自立の学校目標を掲げています。特に鍛える心を磨く部分が健康教育であり、その心を育てる活動の一つに食育の充実を位置付けています。
須坂市の総合計画において「食育の推進」が掲げられており、「命の教育」として食育を位置付けました。しかし、学校で食育は一部の食育に関わる係が行うものという意識があり、教育課題の優先順位としても高いものではありませんでした。そこで文科省指定事業の長野県つながる食育推進事業を受諾し、教職員の意識改革とともに、学校全体で食育を推進する体制を作り上げました。
コロナ禍では、校内の飲食制限、調理実習ができない状態でした。そこで、授業中にこだわり弁当の内容を生徒自身で計画し、家庭学習として自作のお弁当を持参する試みを開始しました。自作弁当を作る際、二つのルールが決められています。①六つの基礎食品群を全て入れる、②その量にこだわる。このルールに基づき年2回自作弁当の日を設定しています。実施した生徒からは、毎日当たり前のように食事をしているが、誰かが考えてくれたり、努力したものを頂いていると有り難みを感じたという感想があり、実践を通じて食に対する意識向上が伺える成果を得ることができた。

パワーポイントのデータはこちら> PPT
パネルディスカッション
コーディネーター

浅輪 華與 氏
- 平成27年 長野県PTA連合会副会長
パネリスト

田中 雅子 氏
- 「NPO法人日本食育協会」食育指導士
- 「NPO法人長野県食育協会」理事・評議員
子どもたちの参画
自作弁当の日の取り組み発表
参加校
須坂市立東中学校
会場
ホクト文化ホール 中ホール(Google Map)
アクセス
- 上信越自動車道 長野ICから約30分
- JR長野駅東口から徒歩約10分
駐車場
約210台(無料)
定員
400人